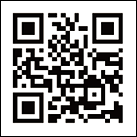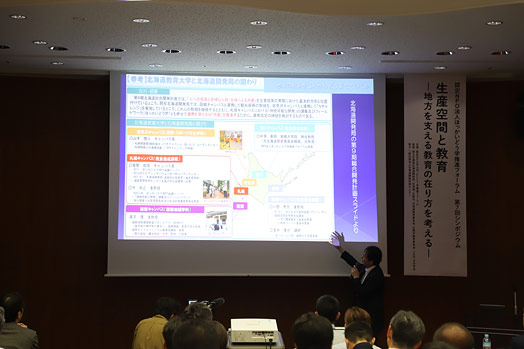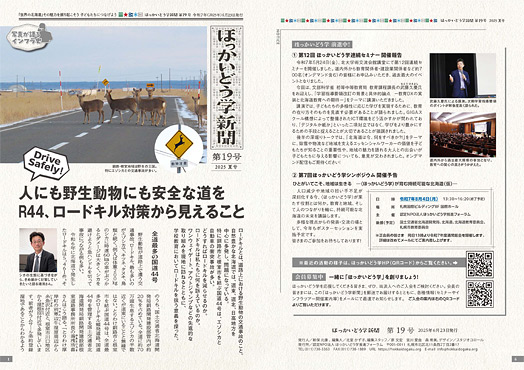今、検討が進んでいる次期学習指導要領では、教科と学校を超えた探究学習が中核になります。厚沢部町立厚沢部中学校では、北海道開発局函館開発建設部と共にこの探究学習にトライアル。中学生が、道の駅を核に厚沢部の未来を考えています。
今回のセミナーでは、中学生にも参加してもらい、人口減少を超えて町の活性化につながる授業づくりについてみんなで考えたいと思います。授業づくりは、教師だけで行う時代ではありません。先生たち、そしてまちづくり関係のみなさまはじめ多くのみなさんとともに新しい時代の学びを創りましょう!
開催概要
■日時:2026年1月22日(木)13時15分~16時10分
■会場:厚沢部町町民交流センター あゆみ 1階交流ホール(厚沢部町新町181-6)
■定員:50名(定員になり次第締切ります)
■締切:1月16日(金)
■参加費:無料
■共催:認定NPO法人ほっかいどう学推進フォーラム・国土交通省北海道開発局・渡島檜山みち学習検討会
■協力:一般社団法人北海道開発技術センター
■後援(予定):北海道、北海道教育委員会、厚沢部町、厚沢部町教育委員会
【お申込み方法・お問合せ】
● プログラム
● お問合せ
一般社団法人 北海道開発技術センター内
特定非営利活動法人ほっかいどう学推進フォーラム事務局
(札幌市北区北11条西2丁目2番17号セントラル札幌北ビル)
TEL:011-738-3363
FAX:011-738-1889
E-mail:info@hokkaidogaku.org