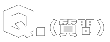
No.770 |
「・いっつも見てると、オホーツク海側や帯広方面では、降る回数は少ないけど一度に一気に降るということが多いような気がするのですが、これはどうしてなんでしょう?テレビで一度見たのですが、去年のオホーツク海側で降らした記録的な大雪がそうだった、日本海側と太平洋側両方に低気圧が停滞するということでいっつもほとんどこうなってるのでしょうか?
・北見や帯広の積雪や降雪量の平年値が知りたいです。調べても分かりませんでした。お願いします。
いっぱいあるので、また頭を整理させてから質問、投稿したいです。よろしくお願いします。こういう何でも聞ける場があってうれしいです。文がながかったので二度にわたって投稿させてもらいました。」
(2005年3月12日 北区内中学1年生の 小原さん からの質問) |
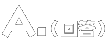 |
1.日本海側と降雪をもたらす仕組みが違います。日本海側に大雪という時には「西高東低の冬型」とか「日本海に筋状の雲」とか天気予報の時間に言っていると思います。この仕組みは「雪を観察しよう」「降ってくる雪」「知ってるかい?」の中にあります。これに対して、道東の雪は低気圧がもたらすものです。低気圧には南からに暖かい湿った空気が入り込むので、発達した低気圧の場合には降雪量が多くなります。去年のオホーツク海側の雪もオホーツク海に低気圧が停滞したためです。
2.平年値:帯広 年間累積降雪量 222cm、最大積雪深 62cm
網走 263cm、54cm。北見には測候所がありません。
3.良い質問をありがとう。感謝します。
(2005年3月14日 雪の先生より) |
 |