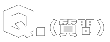
No.520 |
「雪の大きさと気温は、何か関係がありますか?」
(2004年2月7日 三木中学校3年生の 越智さん からの質問) |
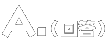 |
雪結晶の形は主に温度によって決まっています。結晶の中でも、−15度付近で成長する樹枝状や−5度付近で成長する針状結晶は成長が速いので、大きな結晶となります。また、雪の結晶同士がくっつきあって大きくなった雪片(大きいものはぼたん雪と呼ばれていますね)があります。0度に近いほどくっつきやすい性質があるので、気温が高いほど大きなぼたん雪となります。
(2004年2月7日 雪の先生より) |
 |