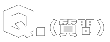
No.460 |
「雪とあられとひょうの違いは何?」
(2004年1月5日 日の出小学校5年生の 小林さん からの質問) |
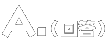 |
雪の結晶とあられの違いは「雪を観察しよう」「降ってくる雪」「知ってるかい?」「雪は雲の中でどうやって大きくなるの?」のところをみてください。くわしくは、あられには2種類あります。温度が低い時には、雪結晶などにくっついた雲粒は直ちに凍ります。これが雪あられで、白色の氷の粒で、球形または円すい形をしています。0℃よりやや低い程度で凍ったり、一度融解して凍結した場合には水が氷表面に薄く広がって凍ります。これを氷あられと言い、透明、または半透明の氷の粒です。
「ひょう」は氷霰が5mmより大きくなったもので、冬にはほとんど見られません。
雲の中を何度も上下して大きくなり、アメリカでは直径約45cm、重さ750g以上のものが観測されたことがあるそうです。
(2004年1月9日 雪の先生より) |
 |