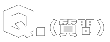
No.380 |
「北海道で使っている、強力なだんぼうや、ストーブは横浜で使っているストーブとどこがどうちがうのですか。
北海道は寒いのにどうして家の中は暖かいのですか。」
(2003年02月14日 横浜市立綱島小学校5年生の 宮崎さん からの質問) |
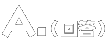 |
横浜ではどんなストーブが使われているのかな?北海道でもストーブやボイラーによる集中暖房が使われていますが、暖房を強力にする必要がありますね。でも、暖房がいくら強くてもすきまだらけではいけませんよね。「雪と暮らそう」の中に「あたたかい家にする方法」というコーナーがありますので(人の手が表示されるところの1つをクリックする)、参考にしてください。
北海道の家は良くなってきましたので、冬にそちらにいくと家の中が寒く感じるという人がたくさんいます。
(2003年02月18日 雪の先生より) |
 |