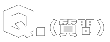
No.114 |
「昔の雪遊びを教えてください。」
(2002年02月08日 横堀小学校4年生の 赤平さん からの質問) |
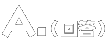 |
僕らの時代は(40才位)、スキー、スケートはもちろん
●その1
空き地に雪の基地を作り,雪合戦
●その2
つららを取って,チャンバラごっこ
●その3
土手や空き地のある雪山でダンボールを尻に敷いてすべる
●その4
プラスチックでできたミニスキー
それから、もっと昔。
これは本(「父さんが小さかったころ」福音館書店)に出ていたことです。
多分、本州の雪の深い所だと思いますが、
●その1
竹スケート(2つにわった竹をはき,スケートのように雪の上を滑る)
●その2
雪かき用の木べら「こすき」の上に乗って,坂を滑る
●その3
そりやスキーを作って,土手などで滑る
●その4
硬く作った雪玉同士をぶつけ合う「きんこ」
※「きんこ」の雪玉の作り方は…
・長靴のかかとで、雪を踏みつける
・靴底の固い雪を拾い、小さな豆つぶぐらいの固い玉を作る
・固くした玉を手で雪の上に転がし,少しずつ大きくする
・長靴の底で転がし、もっと大きく固くする
(2002年02月12日 雪の先生より)
・秋口に古材を山に持ち込んで基地を作り、冬の間は隠れ家にして遊んだ。
・山にみんなで、ソリコースを造りジャンプ台などを作ってレースをした。
250M位の長いコースでした。
・空き地に基地をつくって、雪合戦の開戦場をつくった。
・プラスチックミニスキーでジャンプ。
・つららはよくなめました。
・かまくらもよく作りました。
(2002年02月12日 雪の先生2号より)
先生たちは今、ホームページをもっとおもしろくしようと調査を行っています。その結果を少しだけ先に教えてあげるね。
昔の冬の遊びについて札幌でインタビューしてみました。
・(伏古川)堤防で(川に向かって)スキーやそりに乗るのが楽しかった。あとは、室内遊びだったそうです。(昭和12年頃)
・豊平川の堤防でもスキーやそりを楽しむ人が多かった。(昭和20〜25年頃)
・スキーやそりすべり、雪合戦の他に、雪スケート、塀渡りを楽しんだ。
(昭和20〜25年頃)
先生はちなみに、基地作り・ツララで武器作り、そり・ミニスキー、雪への飛び降り、雪だまころがし(のコース作り)、的あてなど楽しみました。(昭和45〜50年頃)
(2002年02月12日 雪の先生3号より) |
 |