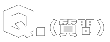
No.086 |
「ゆきのけっしょうのしゅるい」
(2002年02月01日 ながやま4年生の いしいさん・いしださん からの質問) |
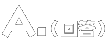 |
成長する環境は微妙に違いますから、形も全く同じものはありません。ただ、雪の結晶は基本的には六角板あるいは六角柱になります。どちらになるかは成長する場所の気温によっています。また、水蒸気の量が多いほど、扇型や樹枝、針など複雑な形になります。
中谷宇吉郎先生は八つの基本形、三一種に分類しました。空から降ってくる固体粒子の国際実用分類では、雪の結晶を角板・星状結晶・角柱・針状・立体樹枝・鼓型・不規則粒子に分けています。
(2002年02月01日 雪の先生より) |
 |