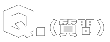
No.039 |
「ゆきは、ふっているのになぜとけるんですか。
とうきょうで、ちょっとゆきがふりました。」
(2001年12月21日 がくしゅういんしょとうか1年生の くろださん からの質問) |
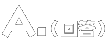 |
1年生ですか。良くかんさつしていますね。
ゆきはれいぞうこにあるこおりのなかまです。れいぞうこのこおりをへやにおいておくとどうなるかな? 山にのぼったことあるかな? 山の上の方が下よりあたたかかった? 冷たかった? 空の上でできたゆきがふってくるとどうなる? これで、わかるかな?
ヒント:先生のいるさっぽろはゆきはとけないよ。はるになるととけるけどね。
(2001年12月21日 雪の先生より)
そらをみると、ゆきはたくさんふってきますね。でも、じめんにおりると ゆきは とけてしまいます。それは、じめんが ゆきよりも あたたかいからなのです。ゆきは こおりやのなかまですから ちょっとでもじぶんよりあたたかいものにふれると すぐにとけてしまうのです。
かきごおりや アイスクリームに にていますね。
先生のすんでいるさっぽろでは、ゆきはとけないよ。それはね、ふゆには じめんが とうきょうより れいぞうこより ずっとさむいので ゆきとじめんが なかよくできるかならんだ。
(2001年12月21日 雪の先生2号より) |
 |