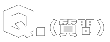
No.002 |
「雪の結晶は、どうして六角形なんですか。」
(2001年8月16日 東京都文京区立金富小学校4年生の 江原さん からの質問) |
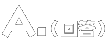 |
江原千絵さん、質問ありがとうございました。
8月はたいへんいそがしかったので、回答が遅れ、もうしわけありません。
「雪の結晶にはどんな種類があるの?」にも書かれているように、 雪の結晶は六角形をした氷の結晶です。氷の結晶は水の分子が規則正しい配列を繰り返してできており、その配列は六角形をしています。それを反映して、雪の結晶は六角形に成長するらしいのですが、実はまだ良くわかっていません。
水分子は1?の3千万分の1位の大きさです。雲の中でこの水分子がたくさん集まって、六角形の雪ができます。本当に不思議ですね。大きくなったら、是非解き明かしてください。
(2001年9月6日 雪の先生より) |
 |